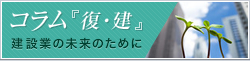2025/01/22
あちこち巡った浅井忠
▼千葉県ゆかりの画家と言えば、近代洋画の先駆者として知られる浅井忠(1856~1907)を思い浮かべる人も少なくないだろう。父は佐倉藩士で、少年時代の1863年から72年まで佐倉市将門町で過ごし、佐倉藩の藩校・成徳書院(現在の県立佐倉高校の前身)で学ぶなど、本県との関わりが深い
▼13歳頃からは佐倉藩の南画家・黒沼槐山に花鳥画を学び、早くもその才能の一端を現した。1875年には国沢新九郎に師事し、翌年、工部美術学校に入学。西洋画を学び、アントニオ・フォンタネージの薫陶を受けた
▼画家に写生はつきものとはいえ、浅井も52歳で病没するまで、精力的に旅に出て写生を創作活動の原動力とした
▼今月19日まで千葉県立美術館で開かれていた特別展「浅井忠、あちこちに行く」でも、同館所蔵の4つの日記―「筑波日記」「従軍日記」「巴里日記」「フォンテーヌブロー日記」―が、多くの作品とともに展示されていた▼これらの日記はデジタルアーカイブとして画像と釈文が公開され、浅井と共に旅しているような臨場感を味わえる。来館できない人々にも浅井の魅力を広く発信しようとする試みともなっている
▼「筑波日記」は、工部美術学校を退学した翌年に従弟の窪田洋平と筑波方面へ旅した際の記録。「従軍日記」は、日清戦争時に従軍画家として戦地に赴いた際の体験を書いている。「巴里日記」は、西洋画研究のために留学したパリでの半年ほどの出来事を綴っている。「フォンテーヌブロー日記」は、1901年5月のフォンテーヌブローからグレーまでの10日間の旅の記録を記している
▼これらの日記には、各時期の旅における浅井の新鮮なまなざしが、多くのスケッチなどとともに書き込まれ、当時の時代背景や浅井の人柄が生き生きと伝わってくる
▼写生への飽くなき探求心はもちろんのこと、その健脚ぶりにも驚かされるが、「もし浅井が現代にやってきたら、どこをどう旅するか」という素朴な疑問も湧いて、考えるほどに興味は尽きない。